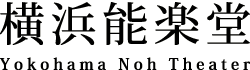2025年03月31日 (月) 能楽関連
〈本舞台創建150年記念掲載〉明治初年 能楽の崩壊と復興-梅若実・宝生九郎・前田斉泰を焦点に
今年2025年は、横浜能楽堂の本舞台が創建されて150年という節目の年となります。10年前の創建140年に開催した企画公演「明治八年 能楽の曙光」のプログラムノートを、節目を記念して掲載します。
江戸時代、幕府の式楽として保護されてきた能・狂言。演じる役者たちは武士の身分と扶持を与えられ、ただ芸道に邁進するだけでよかった。しかし、慶応4年、江戸幕府は終焉を迎え、能役者はこれまで保証されてきた生活基盤、そして演じる場を失ってしまう。幕臣をから明治新政府の朝臣となった者、徳川慶喜を慕って駿河へ下った者、浪人となって他の職業に就いたもの、様々であったが、貧苦の危機に瀕した者が少なくなかった。
「謡の声でもしたら、外から石を投げ込まれる」と言われ、能を演じることもままならなかった時代。そのような状況下でも、芸道を捨てなかった者もいた。その代表が梅若実である。梅若家は江戸時代、観世大夫のツレ家筆頭とされた家柄。実は金融業を営む鯨井家の長男であったが、梅若家の養子に入り家督を相続した。養父が華奢好みで放蕩を尽くしたこともあり、若い頃から様々な苦難に見舞われたが、それを克服し、明治維新の混乱にあっても、厩橋の自宅にある杉板割の二間幅の舞台で明治2年頃から袴能を一般に公開し始めた。当初は、揚幕の布もなく、風呂敷で代用するほどであったが、徐々に環境を整え、明治4年には旧篠山藩主・青山家の舞台を譲り受け、檜舞台を手に入れる。こうして能の再興に向けた兆しが見え始めた頃、さらなる協力者が必要であると感じた梅若実は、板橋に住む宝生九郎のもとを訪れる。
宝生九郎は十六世宝生宗家。32才で幕府の崩壊に遭った九郎は、能の前途を悲観し、芸の道を捨て隠居。商売や農業などに従事していた。実は、九郎に舞台復帰するよう勧める。九郎も一度は捨てた道と容易には承諾しなかったが、実の熱心さに心動かされ、明治6年8月に梅若舞台で袴能「高野物狂」を舞う。そして、明治8年には、梅若舞台で三度、能を舞っている。その一つが、11月21日に実のツレで演じた「蝉丸」である。
世の中が落ち着きを見せ始めると、かつての保護者であった華族たちの間にも能を再び保護奨励しようとする動きが出る。その中心人物の一人が、前田斉泰である。前田斉泰は加賀藩第十三代藩主。前田家は代々宝生流を嗜み、役者を多く抱えてきた。斉泰もまた能に深く傾倒し、廃藩置県に伴い東京へ移住した後も、能役者を支援、また三宅庄市や野村与作といった旧所領の役者を東京に招請し、能の復興に尽力した。また自身も宝生流十五代宗家の宝生弥五郎友于に師事し、能を多く舞っている。現在の横浜能楽堂の舞台となっている根岸・前田斉泰邸の舞台も、能好きの斉泰の老後を慰めるために家臣が相談して建てたといわれる。明治8年4月3日の舞台披きは、梅若実らが出演して華々しく催され、斉泰も「高砂」、「安宅 延年之舞」、祝言「岩舟」の三番を舞っている。
明治6年、岩倉具視が欧米視察から帰国すると、ベルリンで観たオペラと同様に能を国楽として位置づけ、国賓をもてなす際に用いようと考える。そしてその権威づけのため、明治9年4月に明治天皇の岩倉邸への行幸の際に能を天覧に供することになった。その際、岩倉は前田斉泰に相談。斉泰は梅若実に裁量を一任し、これを好機と捉えた実は、自身や斉泰らが出演する番組に臨時の御入能として宝生九郎による半能「熊坂」を加えたという。この催しの成功が契機となり、宝生九郎は本格的に舞台復帰。また天皇や皇族の行幸啓や、国賓を迎える際には能を上演することが通例となり、その後、能は本格的な復興へと進む。その象徴とも言える明治14年の能楽社の設立と芝能楽堂の開場にも、梅若実、宝生九郎、前田斉泰が大きく関わっており、斉泰の発案により「能楽」という言葉が用いられたと言われている。
これまで三人に焦点を当て、明治初年の能楽の歩みに触れたが、実際には、もっと多くの役者の奮闘や支援者の存在があってこそ復興は成り立っている。また一般的に明治期の能の歴史の中で、明治8年が取り上げられることは少ない。宝生九郎と梅若実による「蝉丸」も、当時、当時しばしば行われた人的都合による異流共演の一つとも考えられる。しかし、「蝉丸」が、宝生九郎をもう一度復帰させたいと願う梅若実の熱意により上演され、それが二人の信頼をさらに強くし、翌年の岩倉邸での天覧能に繋がっていることは、想像に難くない。また、前田斉泰邸の舞台も、当初は華族邸宅の舞台の一つとして建てられたが、その後、第二次大戦後の能楽の復興の拠点となる染井能舞台となり、現在は、横浜能楽堂の舞台として数多くの能が演じられることとなるのである。明治の復興、そして今日まで続く能楽の存在の端緒を明治8年の実・九郎・斉泰に求める見方も、また可能なのではなかろうか。
本日の公演が今年、幾つか重なった異流共演の舞台の一つなのか、あるいは、また別の意味を持ってくるのかは、まだ分からない。能楽の危機と再興の歴史と共に140年を生きてきた舞台が、その行く末を見つめていくのだろう。
大瀧 誠之(おおたき・のぶゆき、横浜能楽堂プロデューサー)
平成26(2015)年12月23日 横浜能楽堂舞台140年祭 横浜能楽堂企画公演「明治八年 能楽の曙光」パンフレットより転載