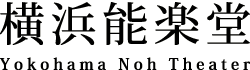2020年02月05日 (水) 能楽関連
「能楽師(狂言方)が案内する横浜能楽堂見学と狂言ワークショップ」を開催しました。
令和2年1月17日(金)に「能楽師(狂言方)が案内する横浜能楽堂見学と狂言ワークショップ」を開催しました。案内役は狂言方大蔵流の山本則秀師とそのお兄さんの則重師です。10:00の回19名、19:00の回17名の皆さまにご参加いただきました。本当にありがとうございました。
当日は、第二舞台で則秀師のお話と体験、見所に移動して鑑賞と舞台説明、楽屋裏見学と本舞台を歩く体験、2階展示廊の「山本東次郎家の装束展」見学、第二舞台に戻り質疑応答という、盛りだくさんなプログラムの2時間でした。中でも、参加者のためだけの狂言「鎌腹」(一部)鑑賞や、山本東次郎家の装束を東次郎家の則秀師が解説する展示見学はとても贅沢な内容でした。

第二舞台での体験

狂言「鎌腹」(一部)の鑑賞

本舞台を歩く体験
全体を通して、則重師と則秀師のお人柄が垣間見えるお話が私はとても印象的でした。そのいくつかをご紹介します。
「狂言の祝言性」
愚かな人間はいませんが、愚かしいことをしてしまう人間がいるものなので、狂言の主題には身の回りのちょっと悪い人が出てきて争いになるものがあります。1人と1人の争いやけんかが大きくなると戦争になってしまいます。戦争という題材を直接扱うのではなく身の回りの争いを題材にして、けんかをしてはいけないという気づきを大切にしているそうです。山本家では、世の中が平和になるように狂言の祝言性をとても大切にしているというお話です。
「楽屋の様子」
楽屋にいる心持としては、既に楽屋にいながら舞台に出ているような厳しさで常に姿勢を正しています。楽屋の間仕切りの戸襖を開けておくのは、誰からどう見られていても恥ずかしくないように気を配り、その日に出演する全ての能楽師全員で舞台をつくりあげる一体感の醸成ということです。

「650年の歴史」
2016年にギリシャのエピダウロスという劇場で古代ギリシャの長編叙事詩「ネキア」を題材にした新作に参加した際のお話です。マルマリノスという演出家が能という手法を取り入れないと実現できないと言っていたそうです。やってみると、能楽師は持っているものですぐにできてしまい、演出家はもっと演出したかったのではないかと・・・。650年の間に積み重ねてきた、様式と型が他には無いからでしょう。能楽にはお金で買えない価値があり、650年の歴史は世界で通用すると思うのです、というお話でした。
最後の質疑応答は、参加者の皆さまの質問内容がすばらしく、山本則重師・則秀師兄弟との双方向のコミュニケーションにより、第二舞台にとてもよい時間が流れていました。いくつかの質疑応答内容をここでご紹介いたします。

Q.台本は変わらないのですか?
A.大事なところは変わらないのですが、変わっている部分もあります。たとえば「かしこまってござる」と「心得ました」はどちらもYESという意味ですが、どちらを使うかは時代で変わることがあります。また、「鎌腹」の結末には2パターンあり、替えの型として伝承しています。
Q.現代の言葉も使用していますか?言葉は変わっているのですか?
A.現代語は使用していません。聞き慣れた言葉だとしたら昔からある言葉なのです。初代・二代・三代の東次郎が生き返って四世東次郎と四人で狂言をやったらすぐにできるくらいの言葉の変化しかありません。
Q.「義経」はなぜ子どもがやるのですか?
A.弱いものの象徴として子どもを置くことで、リアルな気持ちになれるのです。日本人は弱いところに心を動かされる気質があるので、そのための演出です。「屋島」では強い義経なのでこの場合はおとなが演じます。
Q.装束はいつ頃のものなのですか?
A.面は大事にしているのでいたまないため500~600年前のものです。ただし、海外公演の際には古い面の写しを使います。装束は大事にしてもいたんで折り切れができます。今使用しているものはだいたい昭和40年頃から毎年少しずつ作ってきた現在のものまでです。切れると新しいものをつくりますが、古い装束は捨てることはないのでどんどん増えていきます。
Q.個性・持ち味を出すということは考えるのですか?
A.それは考えないです。個性を消した中で残ったもの、消しても出てくるものが個性です。60才までは個性を出してはだめ、60才を過ぎたら+αしてもよいといわれています。
Q.終演の拍手はどうすればいいでしょうか?
A.演者の最後にする、余韻を楽しみたい方もいるのでいらない、拍手の風習は西洋からきたものだからしなくていい、など諸説あります。演者としてはあっても無くてもいいですが、自然な反応が舞台の良し悪しであり、自分の成長にもつながるので、あった方がいいとも思います。
Q.これから狂言を楽しむにあたり参考図書はありますか?
A.いくつかご紹介します。
・「日本古典文学大系 42 狂言集 上 」「日本古典文学大系 43 狂言集 下 」岩波書店
・「狂言のすすめ」玉川大学出版部
・「狂言を継ぐ-山本東次郎家の教え」三省堂
ご参加の皆さまにはアンケートにご協力いただきありがとうございました。来年度のワークショップの企画の参考にさせていただきます。またのご来館を心よりお待ちしております。
はぜの木